
第26回ラウンジ雑学講座
皆さんこんにちは!
Mélia、更新担当の中西です。
ボトルキープは“再来店のエンジン”。一方で、期限切れ・死蔵・破損・記録漏れは資金を凍らせるリスクです。約款(ルール)×CRM(通知)×棚(物理)の3点を整えると、回転率が上がり、キャッシュが回ります。ここではお客様に優しく、店にも優しい運用の作り方を解説します。✨
________________________________________
1. ルール(約款)の設計
• 期限:標準は6ヶ月(地域慣行に合わせ調整)。期限前30日/7日の二段階リマインドを明文化。
• 名入れ:お名前+来店日+開栓日。ラベル+台帳+POSで三重管理。
• 破損/紛失:地震・事故時の取り扱い、ラベル剥離、液面低下(自然減)を約款に明記。
• 共有:同伴者利用の可否、キープの譲渡ルール。
• 持込:持込料・保管可否・破損時責任の線引き。
________________________________________
2. 物理管理(棚・配置・見える化)
• 棚マップ:列×段の座標で管理。VIPは目線高さ、期限迫るボトルは手前へ。
• 名札:防水タグ+耐光インク。期限日は赤、VIPは金の縁取りで識別(演出)。
• 液面ライン:初回開栓時に基準線を記入。自然減を判別。
• 温度・光:直射日光/熱源を避ける。棚背面に拡散照明で視認性UP。
KPI:棚卸所要時間、誤ピック率、期限切れ率。
________________________________________
3. デジタル管理(台帳・POS・CRM)
• 台帳:お客様名/銘柄/容量/開栓日/残量/期限/最終来店日/担当者。
• POS連携:開栓時にバーコード/QR読取→自動で期限計算。
• 通知:公式LINEから期限30日/7日の自動メッセージ。 > テンプレ:「◯◯様のボトル(◯◯)の保管期限が近づいてまいりました。今週は◯/◯(○)〜◯/◯(○)で空きがございます。お好みの割り材もご用意いたします」
________________________________________
4. 回転率を上げる“優しい”販促
• ボトルの日:毎週◯曜日は割り材1セットサービス。在庫が動く。
• ハーフボトル提案:初回は小容量で心理的ハードルを下げる。
• 限定銘柄:季節や記念日に数量限定を入れると来店動機に。
• 共飲み文化:同席者と1杯ずつ楽しむ提案(無理な煽りはNG)。
KPI:月間開栓数、回転率(開栓/在庫)、期限前来店率。
________________________________________
5. 在庫運用(ABCとROP)
• ABC分類:A=高速回転(30日以内)、B=中速(60日)、C=低速(90日以上)。
• ROP(再発注点):リードタイム×平均消費+安全在庫。Aは少量・高頻度、Cは在庫圧縮。
• FIFO:入庫日を大きく表記し、古い順に前出し。
• 棚卸:月末に実棚→台帳突合。差異は“こぼし・試飲・破損”で分類。
________________________________________
6. ロスと不正の予防
• 計量SOP:ショットは30/45mlを徹底。フリーポアは訓練者のみ。
• こぼしログ:氷カランミス、ボトル口の割れ、グラス破損は即記録。
• 監視:バック棚に簡易カメラ(死角・盗難対策)。映像は短期保存で十分。
________________________________________
7. 接客台本(提案・お声がけ)
• 初回提案:「よろしければ本日ボトルでお預かりできます。お名前を入れて、次回は1杯目がすぐにお出しできます」
• 期限前:「前回の◯◯、残り3〜4杯分ございます。来週◯曜が比較的ゆったりしております」
• 飲み切り:「本日少しお得に飲み切りセットご用意できます。割り材3種+氷増量で◯◯円です」
________________________________________
8. 事例|期限通知と“ボトルの日”で回転率1.4→2.1
• 課題:期限切れ多発(毎月15本)、棚卸が長時間化、誤ピックあり。
• 施策:期限通知の自動化、ボトルの日導入、棚マップの座標化。
• 結果:期限切れ-73%、回転率1.4→2.1、棚卸時間-38%。
________________________________________
チェックリスト ✅
☐ 期限・破損・共有の約款がある
☐ 棚マップとタグの色分けが機能している
☐ 期限前30日/7日の通知を出せている
☐ ABC分類とROPで在庫を決めている
☐ こぼし/破損の記録を取っている
________________________________________
まとめ
ボトルは信頼の証であり、資金の形でもあります。ルール・物理・デジタルの三位一体で“動く在庫”に変えれば、現金化の速度が上がります。次回は、顧客カルテとVIPプログラムで関係性の質を高めます。
Meliaでは、一緒に働いてくださるスタッフを募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
第25回ラウンジ雑学講座
皆さんこんにちは!
Mélia、更新担当の中西です。
同じレシピでも“器と温度”で味は別物になります。グラスの厚み/形状、氷の純度/粒度、炭酸のガス圧/開封時間——この3要素を見える化すると、クレームは減り、再現性は上がり、原価も締まる。今日は“おいしさの物理”を現場に落とし込みます。✨
________________________________________
1. グラス(器)の設計思想
• 形状:ハイボールはコリンズ型で気泡上昇を直線的に。ジン&トニックはタンブラーで香りの“逃げ”を抑える。
• 厚み:薄口は口当たりが軽く温度がはっきり、厚口は保冷性が高い。繁忙時は厚口で安定を優先、静かな時間は薄口で“ご褒美感”。
• 前冷:グラスは-10〜0℃にチラーで前冷。食洗後は完全乾燥→冷蔵の順。水滴が残ると炭酸が失活しやすい。
• 洗浄:洗剤残りは香りの大敵。リンス剤薄め+高温乾燥、ポリッシャーはマイクロファイバーを使用。
• 衛生:口元チップの即廃棄ルール。破損時は“破片チェック表”で周辺グラスも入替。
KPI:グラス臭クレーム率、破損率/1000提供、前冷率(前冷グラス使用比率)。
________________________________________
2. 氷(温度と希釈のコントロール)
• 純度:透明度=溶けにくさ。製氷機のフィルター交換と槽の週次清掃で臭い移りを防ぐ。
• 粒度:ロックは大粒(角氷)、ハイボールは中粒で表面積と冷却速度のバランス。
• ドライブレンド:氷を軽く砕いてから再凍結すると、表面整形で溶けにくく口当たりが均一に(実施は食品衛生ルールに適合する設備内で)。
• 攪拌秒数:スピリッツ+氷の15〜20秒攪拌で4〜6℃に。攪拌不足は香りが立たず、やりすぎると薄まる。
• 補充:アイスビンは1/2量を保つ。満杯は上部が常温にさらされ溶けやすい。
テスト:同レシピで氷の粒度を変え、提供後3分の温度と泡持ちを測定→SOP確定。
________________________________________
3. 割り材(炭酸・トニック・ジュース)
• 炭酸:開栓後15分を目安に使い切る。ガン式は夜ごと洗浄、ホース/ジョイントの月次交換をルール化。
• トニック:銘柄で甘味と苦味が大きく違う。ベースのジンとの相性をブラインドテストで決定。小瓶運用で鮮度優先。
• ジュース:搾りは酸化対策(レモンは提供直前搾り、ライムは下処理して真空パック)。
• 水:硬度で味が変わる。コーヒー用の浄水器を共用しない。氷と水は同じ水質に統一。
KPI:炭酸ロス率、開封後使用時間、ブラインド評価スコア。
________________________________________
4. 温度と希釈の“見える化”ダッシュボード
• 提供温度:非接触温度計でランダム5杯/夜をサンプリング→平均値を掲示。
• 泡持ち:注いでから泡が消えるまでの時間を秒で記録(氷粒度別)。
• 希釈率:提供後3分の比重を簡易計でチェックし、薄まりの偏差を把握。
________________________________________
5. トラブルシューティング集
• 炭酸が弱い:グラス前冷不足、氷に水滴、グラス内に脂分。→前冷強化+ガーニッシュ直前に変更。
• 味がぼやける:攪拌過多/氷の粒度が細かすぎ。→攪拌15秒基準に戻す。
• 香りが立たない:グラスの口径/形状ミスマッチ。→ジンはやや広口へ切替。
________________________________________
6. 教育:ブラインド訓練のやり方
• 同じレシピでグラス2種×氷2種×割り材2種=8通りをブラインド。
• 1人ずつ味・香り・食感・温度を言語化。評価表は5段階で統一。
• 月1回のミニ・コンペで優秀者を表彰。楽しさは品質継続の原動力。
________________________________________
7. SOPまとめ
1) グラスは完全乾燥→前冷
2) 氷は中粒、ビンは1/2量維持
3) 攪拌は15〜20秒、注ぎは静かに
4) 炭酸は開封後15分以内、トニックは小瓶
5) 提供温度と泡持ちを毎日記録
________________________________________
8. 事例|グラス運用の見直しで原価-2.1pt・満足度↑
• 前:薄口グラス一辺倒で破損多発、炭酸抜けの苦情。
• 後:ピークは厚口、後半は薄口に時間帯で使い分け。前冷強化。
• 結果:破損-43%、炭酸関連クレーム-68%、粗利率+2.1pt。
________________________________________
まとめ
味は“レシピ”だけで決まりません。器×温度×時間を仕組みに落とし込めば、誰が作っても“うちの味”になります。次回は、リピートの核であるボトルキープと在庫回転を極めます。
Meliaでは、一緒に働いてくださるスタッフを募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
年末年始のお知らせ✨
皆さんこんにちは!
Mélia、更新担当の中西です。
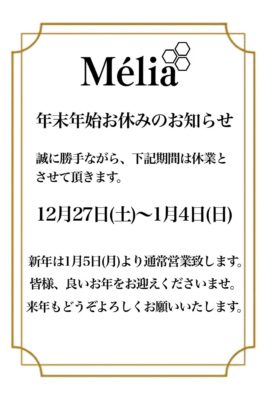
いつも当店をご愛顧いただき、誠にありがとうございます🥂✨
本年もたくさんのお客様に支えていただき、心より感謝申し上げます。
さて、誠に勝手ながら当店では、下記期間を年末年始休業とさせていただきます🙇♀️
📌年末年始 休業期間
📅 12月27日(土)〜1月4日(日)
📌新年の営業開始日
🎉 1月5日(月)より通常営業いたします🍸✨
年末のお忙しい時期、また新年のご予定を立てられている方も多いかと思いますので、ぜひお早めにご確認ください😊
休業期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、営業再開後に順次ご対応させていただきます📩✨
今年もたくさんの素敵な時間を本当にありがとうございました🥰
皆さま、どうぞ良いお年をお迎えくださいませ🎍🌅
来年も変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願いいたします🥂✨
スタッフ一同、1月5日(月)より元気にお待ちしております😊🍸
第24回ラウンジ雑学講座
皆さんこんにちは!
Mélia、更新担当の中西です。
「一生モノのコミュ力」🗣️✨
夜職の魅力は、収入や華やかさだけではありません。
実は、スナック・ラウンジ・バーで働くと、どんな仕事でも活きる “人間力” が鍛えられます💪✨
「コミュ力」と言うと、話が上手いことだと思われがちですが、夜の現場で求められるのはもっと深い力です。
それは、相手の感情を読み、空気を整え、居心地をつくる力。
これが身につくと、人生がかなり楽になります😊🌙
目次
1)“初対面の壁”を越える技術が身につく🚪✨
夜の店では、初対面の人と話す機会が多いです。
最初は緊張します😅
でも慣れてくると、
・相手が話しやすい話題
・触れていいこと/ダメなこと
・会話の温度感
が自然に分かるようになります👀
「話題がない…」ではなく、
相手の“好き・得意・誇り”を引き出す 方向へ会話を運べるようになるんです✨
これは営業、接客、事務、管理職、どんな仕事でも強烈に役立ちます📈
2)“聞く力”は最強のスキル👂🌙
夜職は、会話の主役が必ずしも自分ではありません。
むしろ、お客様が主役の時間。
だからこそ、聞く力が磨かれます。
・話を奪わない
・結論を急がない
・共感はするけど、流されない
・適度に笑いを入れる😂
・相手のテンポに合わせる
この技術は、身につくと本当に強いです🧠✨
人は「理解された」と感じると心が緩みます。
その瞬間を作れる人は、どこでも信頼されます😊
3)気配りは「才能」じゃなく「習慣」🍸✨
夜の店の気配りは、細かいです。
・グラスが空いてないか🍷
・会話に入れていない人がいないか👀
・席の雰囲気が重くなってないか😮💨
・飲みすぎていないか🚫
・タバコや匂いが苦手そうじゃないか🌿
こういう“観察”が日常になります。
最初は意識しないとできませんが、続けるほど習慣になります。
すると、普段の生活でも
「相手が困る前に動ける人」
になっていきます😎✨
4)“場づくり”という高度スキルが手に入る🛋️🎶
夜職は、ただ会話するだけではなく、場全体の空気を作ります。
・賑やかすぎると疲れる
・静かすぎると盛り上がらない
・誰かが目立ちすぎるとバランスが崩れる
この調整ができる人は、ほんとにプロです🏆
スナックなら“家庭的な安心感”、ラウンジなら“品のある華やかさ”、バーなら“世界観の一貫性”。
こういう空気を守るのが仕事であり、同時に魅力です🌙✨
5)見た目・所作・言葉づかいが整う💄👗
夜職は、身だしなみや所作を意識する場面が多いです。
派手になるという意味ではなく、清潔感と品を作る力 が育ちます✨
・姿勢を意識する
・言葉づかいを選ぶ
・相手に合わせた距離感を取る
・自分の見せ方を調整する
これができるようになると、普段の人間関係でも得をします😊
6)“メンタルの扱い方”が上手くなる🧘🌙
夜の店には、いろんな人が来ます。
機嫌がいい日もあれば、疲れている日もある。
だからこそ、感情に巻き込まれない力が必要になります。
・相手の機嫌=自分の価値ではない
・受け止めるけど背負わない
・距離感を守る
この感覚が身につくと、心が安定します🧠✨
※ここはとても大事で、良いお店ほど「スタッフを守るルール」があります🛡️
無理な飲酒やハラスメントを許さない、困ったらすぐ相談できる、など。
安心がある職場ほど、成長も早いです😊
まとめ
夜職の魅力は、
✅ 初対面でも会話を作れる
✅ 聞く力が鍛えられる
✅ 気配りが習慣になる
✅ 場づくりができる
✅ 所作と言葉づかいが整う
✅ メンタルが強くなる
という 一生モノの人間力 が身につくことです🌙✨
「夜の経験」は、昼の人生も強くします😎🍸
Meliaでは、一緒に働いてくださるスタッフを募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
第23回ラウンジ雑学講座
皆さんこんにちは!
Mélia、更新担当の中西です。
「大人の居場所」をつくる仕事✨
「夜の仕事」と聞くと、キラキラしたイメージだけが先行したり、逆に偏見で語られたりしがちです
でも、スナック・ラウンジ・バーの本質は、派手さよりも “人の気持ちを整える場所” をつくることにあります
仕事で疲れた人、家に帰っても気持ちが落ち着かない人、誰かと話したい人。
そういう人が「今日はここに寄ろう」と思える場所が、夜の店です。そこには、昼の世界とは違う“やさしい時間”が流れています✨
目次
1)夜の店は「第三の居場所」になれる➡️
家でも職場でもない、もう一つの居場所。
スナックやバーは、まさに大人の“第三の居場所”です️
・仕事の愚痴を吐いて笑える
・誰にも言えない不安を、少しだけこぼせる
・今日は頑張った自分を、そっと褒めてもらえる
こういう時間って、意外と人生に必要なんですよね。
「ただ飲む場所」ではなく、気持ちを軽くする場所。
それを支えるのが夜職の魅力です
2)スナックの魅力:距離感のあたたかさ
スナックの良さは、なんといっても距離感。
常連さんが多い店では、初めて来た人も“輪”に入りやすい空気があります☺️
ママやスタッフの役割は、盛り上げ役というより “場の温度を整える人”。
誰かが話しすぎたらバランスを取り、静かな人がいたら自然に話題を振る。
全員が心地よくいられる空気をつくるのは、実は高度なスキルです✨
スナックは「人生の先輩」が集まることも多く、
会話の中に学びやヒントが転がっているのも魅力です
恋愛、仕事、人間関係、お金、家族…リアルな経験談ほど参考になるものはありません。
3)ラウンジの魅力:品のある接客と“魅せ方”✨
ラウンジは、スナックより少し“非日常”寄り。
落ち着いた空間、丁寧な所作、きれいなグラス、照明、香り…。
空間全体で「特別な時間」を演出します
ここで磨かれるのは、会話だけではありません。
・言葉遣い️
・姿勢や歩き方♀️
・気配り(タイミング、間、空気読み)
・身だしなみの整え方
こうした“魅せ方”が自然と上達していきます✨
ラウンジの魅力は、ただ明るく盛り上げるより、
相手の心をほどく会話 ができるようになること。
これができる人は、どの世界でも強いです
4)バーの魅力:お酒と会話で“世界観”をつくる️
バーは、店によって世界観がまったく違います。
静かに音楽を聴く店、カクテルが主役の店、スポーツ観戦の店、一人客が多い店♂️…
“空間の個性”がはっきりしているのが魅力です✨
バーテンダーやスタッフは、ただ作業するのではなく、
その店の世界観を守る演出者 でもあります
「今日は強いのじゃなく、やさしい味がいい」
そんな一言から、気分に寄り添う一杯を出せるのがバーのかっこよさです✨
5)「聞く力」が誰かの支えになる
夜職のすごいところは、話術よりも“聞く力”が価値になることです。
人は、正しい答えよりも「分かってもらえた」と感じた時に救われます
・相づち
・目線
・話を遮らない
・否定しない
・でも依存させない距離感
このバランスが取れる人は、本当に強いです✨
お客様から「今日ここに来て良かった」「話して楽になった」と言われる瞬間。
それは、夜職だからこそ味わえる誇りです
6)大前提:健全さと安全が“魅力を守る”️
夜の店の魅力は、安心があってこそ。
・お酒は無理をしない(無理させない)❌
・ハラスメントを許さない♀️
・危険な飲み方をさせない
・大人(20歳以上)だけの場としてルールを守る
こういう姿勢がある店ほど、長く愛されます
夜職の魅力は、派手さではなく 人を大切にする文化 にあります✨
まとめ
スナック・ラウンジ・バーは、ただの“飲み屋”ではありません。
人の心がふっと軽くなる場所、明日を頑張るための居場所をつくる仕事です
誰かの夜を、少しだけ優しくする。
それが夜職の魅力です✨
Meliaでは、一緒に働いてくださるスタッフを募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
クリスマスイベントのお知らせ✨
皆さんこんにちは!
Mélia、更新担当の中西です。
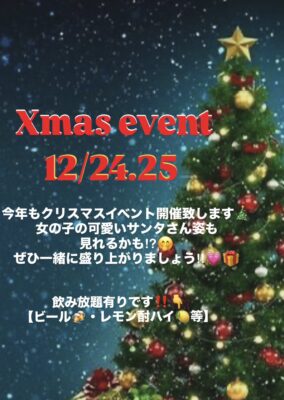
今年もこの季節がやってきました…❄️
街がイルミネーションで彩られて、なんだか気持ちまであたたかくなるクリスマスシーズン🎅🌟
当店でも――
🎄クリスマスイベントを開催いたします!🎄
📅 開催日:12/24・12/25
(2日間限定の特別イベントです✨)
目次
🎅可愛いサンタ姿が見れるかも…!?🤭💕
クリスマスといえば、やっぱりサンタ🎅🎁
当日は、女の子たちの可愛いサンタさん姿が見られるかも…!?✨
いつものラウンジとは少し違う、
**“クリスマス仕様の特別な夜”**を一緒に楽しみましょう🥂💗
「今年のクリスマス、どうしようかな〜」と迷っている方も、
ふらっと寄れる“大人のクリスマス”をご用意してお待ちしています🎄🍸
🍺飲み放題あり‼️(ビール・レモン酎ハイ等)🍋✨
今回のイベントは…
🔥飲み放題ありです‼️👇
✅ ビール🍺
✅ レモン酎ハイ🍋
など、楽しみやすいドリンクもご用意しています✨
みんなで乾杯して、ワイワイ盛り上がりましょう🥳🥂
「飲み放題があると安心して楽しめる!」という方にもピッタリです😆✨
🌙こんな方におすすめです🎁
🎄 クリスマスをひとりで過ごすのは寂しい…
🎄 仕事終わりに少しだけ癒されたい
🎄 せっかくなら誰かと楽しく過ごしたい
🎄 サンタ姿で非日常気分を味わいたい🎅💗
🎄 いつもの仲間と盛り上がりたい🥂
“イベントだからこそ”の空気感で、
笑って、飲んで、今年の締めくくりを最高の思い出にしませんか?🎁✨
📩ご予約・お問い合わせについて
混み合う可能性がありますので、
ご来店予定の方は 事前のご連絡・ご予約がおすすめ です📲✨
(📞お電話/💬LINE/📩DM など、お店の窓口からお気軽にどうぞ!)
🔞大切なお知らせ(マナー・年齢確認のお願い)🙏
当店は 20歳以上の方のみ ご入店いただけます🍸
また、無理な飲酒はせず、みんなで気持ちよく楽しめる夜にしましょう😊🌙
🎄12/24・12/25は、ラウンジでクリスマス🎁✨
一年の中でも特別な2日間。
サンタの夜を、ぜひ一緒に盛り上げましょう🎅💗
スタッフ一同、心よりお待ちしております🎄🥂✨
第22回ラウンジ雑学講座
皆さんこんにちは!
Mélia、更新担当の中西です。
“もう一杯飲みたくなる”のは、味だけが理由ではありません。不安がない導線、迷わない提案、納得できる会計、そして余韻を伸ばすフォロー。この8ステップを台本化+計測で磨くと、再来店率と客単価は同時に伸びます。ここでは、来店前〜退店後までの摩擦を1つずつ削り、誰が担当しても同じ品質になるオペレーションをつくります。✨
________________________________________
ステップ0|問い合わせ・予約(接触前の勝負)
• 導線統一:Googleマップ、Instagram、食べログ、公式LINEは同じ予約リンクへ。個別DMでの“取りこぼし”を防ぐ。
• 即応テンプレ:定休日・料金・席数・喫煙可否・同伴可否を定型文で。最初の返信は3分以内を目標⏱️。
• 期待値調整:セット料金/TAX・SC・滞在目安を明確に。写真3枚(入口/席/看板商品)を自動送付。
KPI:問い合わせ→予約CVR、返信所要時間、直前キャンセル率。
________________________________________
ステップ1|到着・入店(第一印象の黄金の90秒)
• 視認性:表札は“主張しすぎない明るさ”で迷わせない位置。ビル内は矢印サイン。
• 迎えの一言:「お足元お気をつけください。ようこそお越しくださいました」。
• 荷物ケア:コート・傘・大きな荷物は先に預かる。椅子背面にバッグハンガー常備。
チェック:到着→着席を90秒以内。入口で滞る“列”を作らない。
________________________________________
ステップ2|席案内(見え方=安心感)
• 席間:60cm以上を死守。隣席の会話音量を測定(ピーク70dB以下)。
• 温度/照明:入店直後はやや明るめ→着席後に1段階落とす。温度22〜24℃、湿度45〜55%。
• メニュー渡し方:紙+口頭の二段構え。「迷ったらこちらの3品からどうぞ」
________________________________________
ステップ3|初回提案(“迷い”を消す3択)
• 3つの推し:①ハイボール(キレ)②ジンソーダ(香り)③ノンアル(柑橘系)を“違いが分かる”言葉で提示。
• 時間短縮:オーダー受領→提供まで3分以内。氷・グラスは事前プリセット。
• 台本:「今日は涼しいので、香りが立つジンソーダが人気です。ライム強め・弱めお選びいただけます」
KPI:初回提供時間、初回満足度(口頭アンケ)、1杯目→2杯目転換率。
________________________________________
ステップ4|中盤の間延び防止(黄金の15分)
• 観察:グラス残量1/3で声かけ。会話の温度を下げない短い問い:「次はもう少し軽めにされますか?」
• 2杯目導線:味の変化提案(同じベースの割材変更/香草の有無)。
• 小皿:塩味・酸味・甘味の三角形を用意。小腹満たしは滞在時間を+12〜18分伸ばす傾向。
台本:「最初のハイボールがお好みでしたら、次はレモンを少し増やして爽やかに。あるいはジンに切り替えて香りを立てるのもおすすめです」
KPI:2杯目到達率、平均滞在時間、会話中の呼び出し回数(邪魔しない評価)。
________________________________________
ステップ5|会計前の“前置き”説明(納得感の核)
• 口頭で先に:セット料金/TAX・SC/ボトル持越し/明細。印字だけでは誤解が生まれる。
• サプライズ回避:延長が発生した際はその都度確認。「あと30分ですと◯◯円追加になりますが、いかがされますか?」
• レシート/領収書:インボイス対応の有無を先に確認。
KPI:会計トラブル率、説明漏れ件数、口コミでの“会計言及”スコア。
________________________________________
ステップ6|会計(速度×正確性×余韻)
• 所要時間:卓上会計は90秒以内。混雑時は会計専任を置き、配膳と切り離す。
• 支払い手段:現金/各社クレカ/QRはレーン分けで滞りを防止。
• 最後の一言:「本日はありがとうございました。次回は◯◯の新作ジンもご用意しておきますね」
________________________________________
ステップ7|退店・お見送り(余韻を仕上げる)
• 動線:入口付近は明るめ+静音に切り替え。外気との温度差に配慮。
• 見送り:ドアが閉まる直前まで視線で追う。振り返った時に目が合う距離感。
________________________________________
ステップ8|退店後フォロー(記憶の“定着”)
• 24h以内に公式LINEで“お礼+次回予約の軽い提案”。 > テンプレ:「昨夜はご来店ありがとうございました 次回は◯◯(季節限定)をご用意します。◯/◯(○)〜◯/◯(○)の◯時〜◯時で空きがございます。1タップで仮予約できます」
• 誕生日/記念日のタグ付け。VIPは手書きカードを同封(郵送/お渡し)。
KPI:翌月再来店率、LINE開封率/クリック率、紹介来店数。
________________________________________
事例|“迷いゼロ導線”に変えて月次売上+18%
• 課題:初来店の提供遅延(7分超)、会計の説明不足で口コミに“高い”が増加。
• 施策:①推し3品台本 ②会計前の前置き ③LINEの24hテンプレ。
• 結果:初回提供3分台、会計トラブル-70%、翌月再来+9pt、売上+18%。
________________________________________
チェックリスト ✅
☐ 予約導線は一本化されている
☐ 到着→着席90秒を守れている
☐ 1杯目→2杯目の台本がある
☐ 会計前の前置きを言えている
☐ 退店24h以内のお礼メッセージが送れている
________________________________________
まとめ
8ステップは接客の感性論ではなく、再現できる技術です。台本化・計測・振り返りのサイクルで“摩擦”を削れば、安心→満足→再来の流れが太くなります。次回は、味の根幹であるグラス・氷・割り材を科学します。✨
Meliaでは、一緒に働いてくださるスタッフを募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
第21回ラウンジ雑学講座
皆さんこんにちは!
Mélia、更新担当の中西です。
1. 欲しい人物像の言語化
• 笑顔の回復力がある人(ミス後の立て直しが早い)🙂
• 共感の言い換え力(相手の言葉を肯定的にリフレーズ)🗣️
• 衛生観念(手洗い・グラス拭き・片付けの速度)🧼
2. 採用導線
• リファラル:常連/スタッフからの紹介に謝礼。
• 求人媒体:写真は“手元”と“笑顔”、文章は現場の1日で具体化。
• 体験入店:60〜120分で接客→片付け→レジ補助の一巡。
3. 育成90日ロードマップ
• Day1-7:接客台本・メニュー・会計説明の暗記。シャドー。
• Day8-30:1人でカウンター3席担当。SOP準拠の提供速度。
• Day31-90:クレーム一次対応・ボトル管理・締め作業を習得。
4. 評価とインセンティブ
• KPI:提供時間、ミス率、指名/再来の寄与、口コミ言及数。
• インセン:指名/売上の一定%、チーム達成の全員分配も併用。
5. シフト設計
• 週次で客数予測(予約・天気・イベント)を反映。
• ピーク30分に増員→後半削減で人件費最適化。
6. 台本(抜粋)
初回案内:「本日はありがとうございます。ご滞在は1時間ほどでよろしいでしょうか。人気の3品からお選びいただくとスムーズです🍸」
会計前:「本日はセット料とお飲み物2杯、サービス料と税を含めて合計◯◯円でございます。明細はこちらです🧾」
まとめ
人材は“採ってから作る”。台本×SOP×評価の透明性で再現性のある接客を育てます。次回は、来店〜退店の顧客体験を8ステップに分解します。🚪✨
Meliaでは、一緒に働いてくださるスタッフを募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
第20回ラウンジ雑学講座
皆さんこんにちは!
Mélia、更新担当の中西です。
1. メニューの考え方
• 迷わせない4本柱:ハイボール/サワー/ジン/ノンアル。
• 利幅エンジン:ハウスボトル(ウイスキー/焼酎)+割り材。
• 季節の“理由”:気温/湿度/イベントに同期。
2. 原価設計の基礎
• 目標粗利率70〜80%を起点に売価→必要原価を逆算。
• 歩留まり:レモン・ライムは1個あたり搾汁量で実測。
• ロス:氷・炭酸の開封ロスを見積もる。
3. 標準レシピ(SOP)
• 計量(30ml/45mlなど)を全員が同じに。
• 氷の粒度と攪拌秒数で味が変わる——タイマー運用。⏱️
• ガーニッシュは“映え”より香りの一貫性。
4. 在庫とボトルキープ
• ABC分類:A=高速回転、B=準主力、C=長期在庫。
• 棚卸日を“儀式化”して死蔵を可視化。
• ボトル期限をラベル+台帳で二重管理。🏷️
5. 仕入れ交渉の型
• 月次発注の平準化で単価交渉。
• まとめ買いの上限は資金繰りと回転率の交点で。
6. メニュー改定のリズム
• 季節ごとに3品だけ差し替え。常連の“ホーム感”は残す。
7. チェックリスト ✅
• 主要10品の原価率を毎月更新
• 不良在庫率(C在庫/全在庫)を監視
• 提供時間(注文→提供)を計測し、ピーク短縮
まとめ
“売れるメニュー”は味×速さ×粗利の三拍子。SOPでブレを消し、在庫は回して現金化。次回は、人材の採用・教育・評価の“勝てる型”へ。👥📘
Meliaでは、一緒に働いてくださるスタッフを募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
第19回ラウンジ雑学講座
皆さんこんにちは!
Mélia、更新担当の中西です。
1. 立地の見方
• 一次需要:オフィス密度/商談ニーズ、ホテル数、観光導線。
• 二次需要:飲食店の閉店時間、二次会需要、同業集積。
• 夜間動線:駅→繁華街→帰路の流れの中にあるか。
2. 物件チェック
• 階数:路面の可視性 vs 上階の家賃効率。エレベーター有無。
• 間口/導線:入店一歩目の“安心感”。視線が抜ける配置。
• 設備:防音、排気、給排水、分電盤容量、空調能力。
3. 内装動線の黄金律
• 入口→受付→席のS字回遊で“広く見せる”。
• 席間60cm以上でプライバシーと配膳導線を両立。
• 照度の層:入口やや明、席は柔、カウンターは手元明。💡
4. カウンター/テーブルの比率
• カウンター:一人客・短時間。会話密度が上がる。
• テーブル:2〜4名・接待。視線が交差しない角度。
• 売上構成に応じて60:40や50:50で試算。
5. サイン計画
• 過度な主張は避けるが、初来店に迷わせない位置・明るさ。
• Googleマップの案内と現地矢印の一致。
6. 工事のコスト管理
• 躯体に触れない設計でコスト最適化。
• 什器は可動式にして将来のレイアウト変更に対応。
• 音響は投資対効果大:小音量でも“厚み”が出る機材選択。🎵
7. オープン前テスト
• プレオープンで回遊と着席時間を計測。滞在の詰まりを解消。
まとめ
良い立地は“見つける”より“設計する”。導線・照明・音で“居心地”を立ち上げ、席の売上最大化を狙います。次回はメニューと原価の設計図を作ります。📜🥃
Meliaでは、一緒に働いてくださるスタッフを募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()


